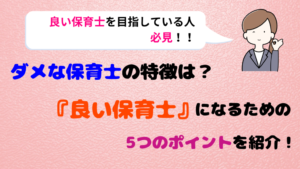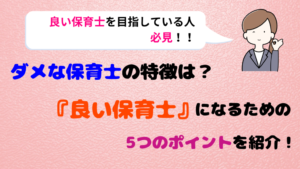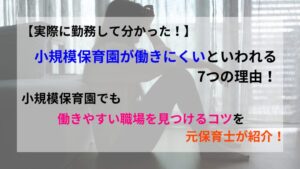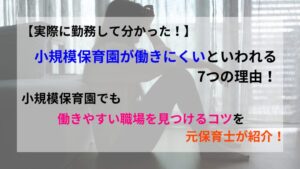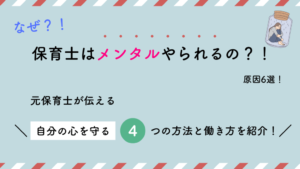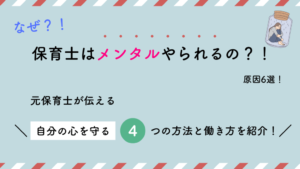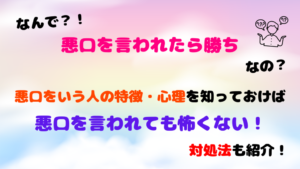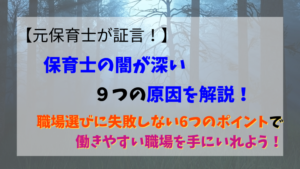「毎日職場に行くのがつらい…」
「仕事のことを考えるだけで、胃がキリキリする…」
「このまま続けていても、人間関係が改善されない気がする…」
このように、保育士としての仕事よりも、人間関係のストレスに心が押しつぶされそうになっていませんか?




































































































































































































保育士の人間関係は、一度こじれると修復が難しいからこそ、辛いですよね。
私もこうした悩みを抱えながら、保育士として働いていました。
毎日「もう限界…。」と感じながらも、保育士として勤務してた私ですが、ある行動がきっかけで、少しずつ心に余裕が生まれるようになりました。
もし今、
「保育士の人間関係がめっちゃ最悪…。」
「人間関係がうまくいかなくて、辛い…。」




































































































































































































など、このように悩んでいるあなたに、私が実際に経験したことや、そこから学んだ対処法をすべてお伝えします。
- 保育士の人間関係が最悪なとき、どうすべき?(5つの選択肢)
- これだけで変わる!保育士の人間関係改善5つのポイント
- 保育士のストレス、どう解消する?私が実践したセルフケア法5選
- それでも改善しないなら?転職という選択肢もアリ!
- 保育士に特化したおすすめ転職エージェント
- 実体験あり!人間関係が最悪になりやすい14の原因
- 放置すると危険!人間関係が最悪なまま働き続ける7つのリスク

































本当は保育の仕事が好きなのに…。
そう思っているからこそ、あなたは悩み、苦しんでいるのではないでしょうか?
そんなあなたが、少しでも前を向いて働き続けられるようなヒントを、このページにぎゅっと詰め込みました。




































































































































































































少しでも心が軽くなり、あなたの悩みを解消するきっかけになれたら嬉しいです。
ひとつひとつ丁寧にお伝えしていきますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
保育士の人間関係が最悪なとき、どうすべき?(5つの選択肢)
「もう、どうしたら良いのかわからない…」
「周りの保育士の目が怖くて、仕事に行きたくない…」
「誰も自分のことをわかってくれない…」
保育士として働く中で、職場の人間関係がうまくいかないと、それだけで毎日がとても苦しく感じてしまいますよね。
子どもと向き合いたい気持ちはあるのに、一緒に働く保育士との関係がストレスの原因になっていると、本来の仕事にも集中できなくなってしまいます。




































































































































































































私自身も、保育士同士の人間関係に悩み、心が折れそうになったことが何度もありました。
あなたも今、「どうしたらこの状況を乗り越えられるのか」と悩んでいるのは、本当は保育にもっと集中したいという気持ちがあるからではないでしょうか?
しかし、人間関係の問題を解決させるためには、残念ながらすぐに解決できるわけではありません。

































じゃぁ、このまま苦しいまま働くしかないの?




































































































































































































いいえ、そうではありません。
人間関係に悩んだときにすぐできる行動や、心の持ち方を少し変えることで、今の状況がラクになることもあります。
ここからは、今の環境で工夫してできることから、環境自体を見直す選択肢まで、段階的に5つの方法を紹介します。
- 仕事上の関係と割り切る
- 信頼できる人に相談する
- 距離を置く・深く関わらないようにする
- 業務や保育に集中して“心の居場所”を作る
- それでもつらいなら → 転職という選択肢




































































































































































































この5つに関して、詳しく説明していきますね。
1.仕事上の関係と割り切る
保育士の人間関係が最悪なとき、まず試してほしいのが『仕事上の関係と割り切る』という考え方です。
「人間関係をよくしよう」と頑張ってみたけれど、相手が変わらなければ何も変わらない…。
どうにか関係をよくしようと声をかけても、反応が冷たい…。
雰囲気をよくしようと笑顔で接しても、逆に気を使いすぎて疲れてしまう…。




































































































































































































「もっと歩み寄れたら…」と思っても、人間関係は、自分だけの努力ではどうにもならないことも多いので、難しいところですよね。
そんなときに試してほしい考え方のひとつが、『仕事上の付き合いと割り切ること』です。
一緒に働いていると、「仲良くしなきゃ」「うまくやらなきゃ」と誰しもが思ってしまうのではないでしょうか?
もちろん、それは悪いことではありません。
しかし、そのように思いすぎてしまうことで、保育士同士の人間関係に敏感になってしまう原因となり、結果的に自分の気持ちが苦しくなってしまうんです。




































































































































































































「もう、頑張るのやめたい…」
このように思ったとき、当時付き合っていた夫に、こんなことを言われたんです。


仕事上の関係なんだから、無理に仲良くする必要はないんじゃない?
相性が合う・合わないもあるし、割り切ってみるとラクになるかもよ?
このように言われましたが、もちろん、すぐに割り切れるわけではありませんでした。
でも、「これは仕事」と少しずつ意識するようになってから、関係に過度な期待をしなくなり、自分のペースを保てるようになっていったんです。
少しずつ気持ちがラクになっていく中で、「これって案外大事な考え方かもしれない」と思うようになりました。




































































































































































































実際に意識してみて、私はこんなメリットを感じることができました。
- 比べなくなる
他人の言動が気になりすぎず、自分のペースを保てるようになる - 目の前の仕事に集中できる
子どもたちに目を向けやすくなり、やりがいも感じやすくなる - プライベートを切り分けて楽しめる
仕事のモヤモヤを家に持ち込まずに済む - ストレスが溜まりにくくなる
人に対する過剰な期待が減り、気持ちが安定しやすくなる
もちろん、こうしたメリットがあっても、ストレスがゼロになるわけではありません。
でも、「仲良くしなきゃ」「うまくやらなきゃ」という考え方を少し変えるだけで、自分の心がラクになる場面もあるはずです。




































































































































































































人間関係で悩んでいるときに、「割り切るなんて無理…」と思うかもしれません。
もしかしたら、少し気持ちが楽になるかもしれませんよ。
2.信頼できる人に相談する
保育士の人間関係が最悪なときはどうすべきか、次に試してほしいのが『信頼できる人に相談する』ということです。
「誰に相談したらいいのかな…。」
「相談しても、誰もわかってくれないかもしれない…。」
「自分のことなんだから、自分で解決しないと…!」
こんなふうに思って、相談するのをためらっていませんか?




































































































































































































私も「誰にも頼れない」「強くならなきゃ」と思い込んでしまい、誰にも相談できず、1人で悩みを抱え込んだことがあります。
人間関係に悩んでいるとき、誰にも話せずに一人で抱え込むのは、とても辛いものです。
たとえ、

































でも、まだ相談しなくても大丈夫!
このように思っていても、気づかないうちにストレスが積もり、心が限界に近づいてしまうこともあります。




































































































































































































私もこのような経験をし、「もっと早く相談していればよかったな…。」と思ったんです。
だからこそ、安心して話せる・相談できる相手を見つけることが、とても大切なんです。
もちろん、誰かに話したからといって、すぐに悩みが解決するとは限りません。
しかし、信頼できる人に話すことで、気持ちが楽になるのと同時に、自分の心の整理になることも多いです。




































































































































































































私自身、話すまでは『何も変わらない』と思っていたんです。
しかし、いざ言葉にしてみると心が少し軽くなり、相手の返してくれた一言が、考え方を変えるきっかけにもなったんです。
こうした経験をしたからこそ、信頼できる人に相談するメリットは4つあると感じました。
- 安心できる
「わかるよ」「つらかったね」と共感してもらえるだけで、気持ちがラクになる - 視点が変わる
自分では気づけなかった考え方や選択肢をもらえることがある - 一人じゃないと気づける
「私も悩んだことがあるよ」と言ってもらえるだけで、孤独感がやわらぐ - 現実的な対処のヒントがもらえる
話す中で、自分がどう動くべきかが見えてくることもある
信頼できる人に相談したとしても、すぐに答えが出ないかもしれません。
しかし、誰かに話すことで
- 話せてよかった
- わかってもらえた
- また頑張ろう!
- 自分には味方がいる!
と感じることができ、結果的に心が軽くなることもあります。




































































































































































































辛さを言葉にすることは、自分を大切にすることでもあります。
どうかひとりで抱え込まずに、誰かの力を借りてみてくださいね。
3.距離を置く・深く関わらないようにする
保育士の人間関係が最悪なときはどうすべきか、3つ目に試してほしいのが『距離を置く・深く関わらないようにすること』です。
一緒に働く仲間なので、できることなら
- 人間関係を良好に築いていきたい
- 協力して仕事に取り組んでいきたい
このように感じて、苦手な人とも頑張って関わろうとしていませんか?




































































































































































































そう言っている私も、同じでした。
しかし、人それぞれ価値観や考え方、年齢や経験してきたことも違うので、どうしても合わない人もいます。
無理に合わせようとすると、人間関係に対するストレスが溜まり、疲れてしまうリスクも高いです。
そのため、無理に仲良くなろうとせず、距離を置き、深く関わらないことも対処法のひとつです。
かといって、社会人としての最低限の挨拶や報連相はしっかり行う必要はありますが、それ以上は踏み込みすぎないようにしましょう。




































































































































































































無理に関わらないことで、実はこんなふうにラクになるんです。
- 心の負担が減る
無理に気を使わなくてよくなり、自分の気持ちに余裕ができる - 自分の仕事に集中できる
相手の反応に一喜一憂せず、保育に集中できる時間が増える - トラブルの回避につながる
距離があることで、余計な摩擦を避けやすくなる - 人付き合いの線引きができる
「誰とでも仲良くしなきゃ」という思い込みから解放される




































































































































































































私も以前、無理に関わろうとして疲れた経験がありました。
少し距離を取ったことで、自分の感情が落ち着き、仕事にも集中できるようになりました。
人と距離を取ることは、決して悪いことではありません。
それは逃げではなく、自分を大切にするための工夫なんです。




































































































































































































あなたがラクでいられること、自分の心を守ってあげることが1番大切なことですよ。
4. 業務や保育に集中して“心の居場所”を作る
保育士の人間関係が最悪なときはどうすべきか、4つ目に試してほしいのが『業務や保育に集中して“心の居場所”を作ること』です。
人間関係で悩んでいると、
「業務や保育に集中している余裕なんてないよ…」
「職場のすべてが嫌で仕方ない…。」
など、ついつい思ってしまいますよね。
しかし、どんなに人間関係が辛くても、子どもたちと過ごす時間の中には、笑顔になれる瞬間があったり、楽しいことや嬉しいこともあったりしませんか?




































































































































































































私にも人間関係に苦しんだ経験がありますが、ずいぶん子どもたちに助けられました。
保育に向き合っている時間は、自然と仕事に集中できていたんです。
保育に集中することで、4つの良いことがあります。
- 達成感を得られる
目の前の子どもたちの成長や反応が、自分のやりがいにつながる - 周囲のことが気にならなくなる
自分の保育に没頭することで、他人の視線から少し距離を取れる - 前向きな気持ちになれる
自分ができたことに目を向けることで、「今日も頑張れた」と思えるようになる - やりがいを再確認できる
「やっぱり保育が好き」と感じる瞬間を思い出せることがある




































































































































































































私も、保育士同士の人間関係が辛いときほど、あえて保育そのものに目を向けるようにしていました。
子どもたちの笑顔や、日々の小さな成長を感じられることが、本当に大きな支えになっていたんです。
保育士同士の人間関係は、どうしても難しくなりがちで、逃げ出したくなるときもあります。
それでも、子どもたちと過ごす時間の中には、あなたの心がほっとできる瞬間が必ずあるはずです。




































































































































































































保育は、子どもたちの成長を間近で感じられる、やりがいのある仕事だからこそ、まずはその時間の中に、あなた自身が安心できる“心の居場所”を見つけてみてくださいね。
5.それでもつらいなら → 転職という選択肢
保育士の人間関係が最悪なときはどうすべきか、最後の手段として『転職という選択肢』です。
さまざまな方法を試したとしても、
「ちょっと限界…。」
「ここでずっと働いていくのは辛い…。」
と、人間関係のストレスが重くのしかかっている方もいるのではないでしょうか?
そうした状況で、「まだ頑張れる」と思って無理をすると、あなたの心が壊れてしまいます。




































































































































































































そうなってしまう前に、「今の職場にこだわらない」「転職を視野に入れる」といった選択肢を入れてみてください。
しかし、中には
「逃げるみたいでイヤ」
「今担当している子どもたちのためにも、年度内は頑張りたい」
このように感じて、無理を重ねてしまう方もいるかもしれません。
ですが、それは危険です。




































































































































































































実は、私も人間関係のストレスを抱えながら、無理して勤務した結果、適応障害となり、半年〜1年ほど心療内科に通ったことがあります。
とても辛い経験でした…。
私のように、自分の心が壊れてしまってからでは遅いんです。
自分の心を守るために転職をすることは、決して悪いことではありません。




































































































































































































転職を前向きに考えるうえでのメリットは、次の4つです。
- 人間関係をリセットできる
新しい職場では、ゼロから関係を築けるチャンスがある - 環境が変わると気持ちも変わる
職場が変わることで、心がラクになる人も多い - 自分に合った園を見つけられる
自分の価値観に合った保育方針や職場環境を選ぶことができる - 保育のやりがいを再確認できる
合わない環境から離れ、自分に合った職場に勤めることで、「やっぱり保育が好き」と気づけることもある




































































































































































































私も年度内に退職した経験があり、子どもたちに申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。
転職は決して簡単な決断ではありません。




































































































































































































でも、だからこそ立ち止まって考えてみてほしいんです。
もしあなたが、
- 「今のままで本当にいいのかな?」
- 「もっと自分に合った職場で働きたい。」
と、感じているなら、一度立ち止まって、違う選択肢にも目を向けてみる価値はあると思います。
少し立ち止まること、転職を視野に入れることは、後ろ向きなことではありません。




































































































































































































自分がどうしていきたいか、じっくり考えることも大切ですよ。
この章では、保育士の人間関係が最悪なときに、心と体を守るための5つの選択肢を紹介しました。
- 仕事上の関係と割り切る
仕事上の関係と考え、必要以上に関わりすぎないことで心がラクになる - 信頼できる人に相談する
ひとりで抱え込まずに話すことで、気持ちが整理され、新たな視点が得られる - 距離を置く・深く関わらないようにする
無理に仲良くしようとせず、適度な距離感を保つことでストレスを減らせる - 業務や保育に集中して“心の居場所”を作る
人間関係にとらわれず、子どもたちとの関わりを心の支えにする - それでもつらいなら → 転職という選択肢
無理を続ける前に、環境を見直すことも大切
転職は自分を守る手段のひとつである
職場の人間関係がうまくいかないとき、気持ちがふさぎこんでしまうのは自然なことです。
だからこそ、今の環境の中でできる工夫や、環境そのものを変えるという視点も持っておくと、心が少しラクになります。
たとえ、

































人間関係を変えるなんて無理かも…。
このように感じていたとしても、小さな行動の積み重ねで状況が変わることもあります。
それでも難しいときは、「他に自分に合う園があるかもしれない」と、転職に向けて一歩踏み出してみるのも選択肢のひとつです。
しかし、

































今すぐ転職したいわけじゃないけど、他にどんな園があるのかだけでも知っておきたい…




































































































































































































もし、このように思うことがあるのなら、転職エージェントを“情報収集の場”として活用してみるのも1つの方法です。
転職エージェントは、無理に転職を勧めることはしません。
今抱えている悩みをじっくり聞いてくれるので、気持ちが軽くなることがあります。




































































































































































































私も転職エージェントを利用したことがありますが、強引に転職を勧められることはありませんでした。
現在、無料で利用できる転職サポートも多く、保育士専門のエージェントなので、あなたに合った園や働き方を一緒に考えてくれるはずです。




































































































































































































ここで、おすすめの転職エージェントを5つ紹介しておきます。
- 【
保育のお仕事】
求人数が多く、非公開求人も豊富。
全国対応可能 - 【保育専門求人サイトほいく畑】
未経験・ブランクありOKの求人が充実
コーディネーターのサポートも丁寧 - 【
レバウェル保育士】
LINEでやりとり可能
気軽に相談しやすいサポート体制が魅力 - 【保育エイド】
人間関係に悩んで辞めた方向け
穏やかな職場を優先して紹介してくれる - 【保育バランス】
家庭やプライベートを大切にしたい方向け
働きやすさ重視の求人が中心




































































































































































































ちなみに、これらの中でも「保育のお仕事」と「保育バランス」については、実際の口コミや評判をまとめた記事があります。
もちろん、無理に転職を決めなくて大丈夫です。
自分の気持ちに耳を傾けて、「合う職場があるかもしれない」という選択肢を持つだけでも、少し心がラクになるはずです。




































































































































































































まずは相談だけでもOKです。
『話すだけで心が軽くなる』という声も多いので、今の状況を変える第一歩として、気軽に利用してみてくださいね。
これだけで変わる!保育士の人間関係を改善させる5つのポイント


「保育士の人間関係って、本当に難しいなぁ…」
「どうしたら、今の人間関係を少しでも良くできるんだろう…?」
本来、保育士の仕事は、単に子どもを預かるのではなく、
- 子どもの健やかな成長・発達を支援する
- 一人ひとりの個性や気持ちに丁寧に寄り添う
- 保護者と信頼関係を築きながら連携する
- 集団生活の中で社会性や生活習慣を身につけられるよう導く
- 安全で安心できる環境を整え、守る
といった、大切な役割があります。
ですが実際には、保育士同士の人間関係に疲れ切ってしまい、毎日が辛いと感じている方も多いのではないでしょうか?




































































































































































































そう聞いている私にも、こうした経験があります。
人間関係のストレスが続くと、仕事に行くのが億劫になったり、同僚のちょっとした一言に傷ついたりして、ますますつらく感じてしまいますよね。
人間関係の悩みをすぐに解決するのは、決して簡単なことではありません。
でも、これからご紹介する5つのポイントを実践していけば、少しずつ職場の雰囲気や気持ちがラクになっていくかもしれません。
この章では、保育士の人間関係を改善するために大切な5つの行動を紹介します。
- しっかり挨拶をする
- 報連相を怠らない
- コミュニケーションを取るようにする
- 相手の立場を考えた行動・言動を行う
- 感謝の気持ちを忘れず相手に伝えること
これらのポイントを意識するだけで、人間関係のストレスが少し軽くなったり、職場の空気が変わっていくかもしれません。




































































































































































































それでは、ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
1.しっかり挨拶をする
保育士の人間関係を改善するために、まず意識したいのが『しっかり挨拶をすること』です。

































挨拶なんて、社会人として当然のことだし、ちゃんとしてるよ?
おそらく、多くの方は、このように思ったことでしょう。
たしかに、挨拶は社会人としてのマナーであり、基本中の基本ですが、ただ形式的に挨拶するだけでは、人間関係の改善にはつながりにくいです。

































どういうこと?
挨拶をするときは、『相手にしっかり伝わるように心を込めて挨拶することが大切』なんです。
たとえば、あなた自身が挨拶される側になったとき、
- 笑顔でハキハキとした挨拶
- 元気がなく、小さい声の挨拶
どちらの挨拶の方が嬉しいですか?




































































































































































































私は『笑顔でハキハキとした挨拶』をしてもらった方が、嬉しいです。
きっとあなたも、そう感じるのではないでしょうか?
挨拶をすることは、社会人としてのマナーとはいえ、笑顔で心を込めて行うことによって、自然と笑顔になったり、その後の会話がスムーズになることが多いです。
そのため、挨拶がなかったり、声が小さすぎて聞こえなかったりすると、
- 「話しかけにくいな…。」
- 「なんだか冷たい感じがするかも…。」
と、少し距離を感じてしまうこともあります。




































































































































































































挨拶だけで、このような印象を持たれてしまうことは、非常にもったいないですよね。
挨拶は特別なスキルや勇気が必要なものではなく、自分からすぐに始められる行動です。
相手の目を見て、明るく、気持ちのこもった挨拶を心がけることで、少しずつ信頼関係が生まれていきます。




































































































































































































今日からほんの少し、“挨拶の仕方”を見直してみてください。
たったそれだけでも、職場の空気が変わっていくかもしれませんよ。
2.報連相を怠らない
保育士の人間関係を改善するために、次に意識したいのが『報連相(報告・連絡・相談)を怠らないこと』です。

































えっ、ちゃんと報連相してるつもりだけど…?
そう思った方も多いかもしれませんね。
たしかに、報連相は社会人として基本中の基本ですし、保育の現場では当たり前のように行われていることかもしれません。




































































































































































































でも、「つもり」になっていませんか?
実は、“報連相がしっかりできている人”と“なんとなくやっている人”では、周囲からの信頼や人間関係に大きな差が出てしまうこともあるんです。




































































































































































































たとえば、こんな場面はどうでしょうか?
- 保護者から伝言を受けたけれど、同じクラスの先生に伝え忘れていた
- 子どもの体調の変化に気づいたけれど、報告するタイミングを逃してしまった
- 自分だけで判断してしまい、他の職員と連携が取れなくなってしまった




































































































































































































子どもの命を預かる保育の仕事では、こうしたことはあってはいけないですよね。
このように、1つひとつは小さなことでも、積み重なると「信頼できない」「報連相ができない人」という印象を持たれてしまうリスクがあります。
逆に、ちょっとしたことでも「○○があったので、念のため共有しておきますね」とひと声かけるだけで、
- 「しっかりしてるな」
- 「この人と一緒に働くと安心できるな」
と、信頼が積み重なっていくのです。
もちろん、報連相ができていると、仕事のミスも防げますし、職員同士の連携もスムーズになります。




































































































































































































それはつまり、良好な人間関係にもつながるということなんです。
報連相のポイントは、『丁寧に・こまめに・相手の立場も考えて伝えること』です。
決して難しいことではありませんが、「意識してやるかどうか」で結果は大きく変わります。




































































































































































































今日からほんの少し、“伝えることのタイミングや丁寧さ”を意識してみてください。
それだけでも、周囲との信頼関係がグッと深まり、人間関係のストレスが減っていくかもしれませんよ。
3.コミュニケーションを取るようにする
保育士の人間関係を改善するために、次に意識したいのが『コミュニケーションを取ること』です。

































ちゃんと話してるし、必要なことは伝えてるけれど…。
そう思った方もいらっしゃるかもしれませんね。
保育の現場では、報連相や業務のやりとりなど、必要な会話は毎日交わしています。




































































































































































































でも、それだけで「信頼関係」って築けると思いますか?
実は、“必要な会話だけ”で済ませていると、相手のことがよくわからなかったり、自分のことも理解してもらえなかったりして、どこか壁を感じてしまうことがあります。
たとえば、
- 相手が怒ってるのか、ただ忙しいだけなのかわからなくて気を使ってしまう
- 話しかけたいけど、どんな人かよく知らないから距離を置いてしまう
- 実はお互い似たような悩みを持っていたのに、話す機会がなかった
こうした経験、思い当たることはありませんか?




































































































































































































私にも経験があります。
こうした“ちょっとしたすれ違い”が、関係をギクシャクさせてしまう原因になることもあるんです。
だからこそ、
「○○先生、最近どうですか?」
「今日の給食、おいしかったですね~。」
といった、ちょっとした雑談や、仕事以外のやりとりもとても大切です。




































































































































































































私も何気ない会話でも、相手との距離がぐっと縮まったことがあります。
実は、コミュニケーションって、特別なテクニックが必要なわけではないんです。
- 相手のことをもっと知ろうとする気持ち
- 自分のことも少しだけ伝えてみる勇気
この2つがあれば、少しずつ関係は変わっていきます。
もちろん、無理して会話を増やす必要はありません。




































































































































































































でも、“ちょっとしたやりとりを大切にする”ことを意識するだけで、職場の雰囲気も、自分の気持ちも、きっと少しずつ変わっていくはずです。
ぜひ、試してみてくださいね。
4.相手の立場を考えた行動・言動を行う
保育士の人間関係を改善するために、次に意識したいのが、『相手の立場を考えた行動・言動をすること』です。
ですが、あなたは、

































ちゃんと気をつけてるし、むしろ毎日気を使いすぎて疲れてるんだけど…。
と、こんなふうに感じているかもしれませんね。




































































































































































































すでに、配慮を心がけているなら、それは本当に素晴らしいです。
でも、自分では気をつけているつもりでも、残念ながら、受け取る側によっては「配慮が足りない」と思われてしまうこともあります。

































え…?じゃあ、私が気をつけていたことは意味がなかったの…?




































































































































































































いいえ、そういうわけではありません。
気づかいや優しさは、すぐには伝わらなくても、きっと誰かの心に残っているものです。
でも、もう少しだけ意識してみることで、職場の空気がさらにやわらかくなっていくかもしれません。




































































































































































































たとえば、こんな気遣いをするのはどうでしょう?
- 忙しそうな先生に声をかけるタイミングをちょっと待ってあげる
- 誰も手が回らないタイミングでさっとゴミを片づけておく
- 子どもに関する大切なことはきちんと報告・共有する
- 忙しいときこそ、笑顔の挨拶で空気をやわらげてみる




































































































































































































ちょっとした気づかいでも、人間関係がぐっと変わることってあるんですよ。
保育の仕事は、一人で完結するものではなく、みんなで協力して進めることが最も大切だからこそ、
- 相手の立場だったら、どう感じるかな?
- 今、自分にできることって何だろう?
こうして視点を変えるだけで、関係がやわらぐきっかけになることもあります。
ぜひ、今日からほんの少しだけ、“相手を思いやる視点”を意識してみてください。




































































































































































































たったそれだけでも、職場での空気や人との距離感が、きっと少しずつ変わっていくはずです。
5.感謝の気持ちを忘れず相手に伝えること
保育士の人間関係を改善するために、最後に意識したいのが『感謝の気持ちを忘れず相手に伝えること』です。

































えっ、何かしてもらったら、ちゃんと「ありがとうございます。」って言ってるよ?
おそらく、多くの方は、このように感じたのではないでしょうか?
感謝の言葉を伝えることは、社会人として当たり前のことですし、すでに自然とできている方も多いかもしれません。




































































































































































































もちろん、私もそのうちの1人です。
でも、形式的な「ありがとう」だけでは、本当の意味での信頼関係にはつながりにくいんです。

































どういうこと?
感謝の気持ちを伝えるときは、ただ口にするだけでなく、“相手に伝わるように気持ちを込めて伝えることが大切“です。
気持ちのこもった「ありがとう」には、想像以上の力があります。




































































































































































































たとえば、あなた自身がこう言われたとき、どちらが嬉しいと感じるでしょうか?
- 「あ、ありがとう(目も合わせずにボソッと)」
- 「ありがとう!本当に助かりました!(笑顔で目を見て)」
きっと、多くの人が後者の方が嬉しいと感じるのではないでしょうか?




































































































































































































私も笑顔で「ありがとう」と言われる方が嬉しいですし、「役に立ててよかった」と感じます。
感謝の気持ちをしっかり伝えることは、3つのメリットがあります。
- 相手との距離がグッと縮めてくれる
「気づいてくれて嬉しい」と感じてもらえることで、自然と信頼関係が深まる - 「またこの人の力になりたい」と思ってもらえる
感謝の言葉が、相手のモチベーションや関わり方を前向きに変えてくれる - 職場の空気や、人間関係を良くしてくれる
感謝が広がることで、職場全体にやわらかい雰囲気が生まれる
「ありがとう」は、一番シンプルで、一番効果的なコミュニケーションです。
感謝の気持ちひとつで、人間関係はぐっと前向きに変わっていきます。
ですので、今日からほんの少し、“感謝の伝え方”を意識してみてください。




































































































































































































たったそれだけでも、職場の人間関係がふっと温かくなる瞬間が増えるかもしれませんよ。
この章では、保育士の人間関係が最悪なときに、関係性を少しずつやわらげていくための5つの行動ポイントを紹介しました。
- しっかり挨拶をする
笑顔で気持ちのこもった挨拶が、信頼関係の第一歩になる - 報連相を怠らない
小さなことでも丁寧に伝えることで、安心感と信頼が積み重なる - コミュニケーションを取るようにする
業務連絡だけでなく、ちょっとした雑談が関係性を深めてくれる - 相手の立場を考えた行動・言動を行う
少しだけ視点を変えることで、職場の空気が和らぐ - 感謝の気持ちを忘れず相手に伝えること
気持ちのこもった「ありがとう」が、人との距離をぐっと縮める
職場の人間関係は、残念ながら、すぐに改善されるものではありません。
ですが、日々のちょっとした心がけで、少しずつ人間関係が良い方向に変わっていくはずです。
今回お伝えした5つのポイントは、どれも特別なスキルや大きな努力を必要としない、シンプルな行動ばかりです。
保育士の人間関係について、

































なんとか変えたい…!
そう感じているときこそ、できることから少しずつ取り入れてみてください。




































































































































































































その小さな一歩が、職場の空気を少しずつ変えていくはずです。
保育士のストレス、どう解消する?私が実践したセルフケア法5選


「なんだか、ずっと気が張りつめてる気がする…」
「家に帰っても、職場のことばかり考えてしまう…」
「疲れているのに、うまくリフレッシュできない…」
保育士として働いていると、子どもたちの日々の成長を感じたり、笑顔に元気をもらえたりと、楽しさややりがいを感じる場面もたくさんあります。
でも、ふとした瞬間に、心も体も限界に近づいているような感覚におそわれることはありませんか?




































































































































































































私も、保育士同士の人間関係と業務の忙しさが重なったことで、疲れがなかなか取れず、そのまま翌日の勤務をすることがよくありました。
さらに、休みの日でさえ仕事のことや人間関係が頭から離れず、気づかないうちに気持ちがどんどん追い込まれていったんです。
ですが、そんなときこそ大切にしたいのが『自分自身のケア』、つまり、自分の心と体をしっかり労ってあげることです。
保育士として働いていると、自分のことを後回しにして頑張り続けてしまう方が多いです。
だからこそ、意識して取り入れてほしいセルフケアの習慣があります。




































































































































































































この章では、私自身が実践して「これをするだけでも、少しラクになれた」と感じた、5つのセルフケア法を紹介します。
- 自分の時間を作る
- 心を許せる人と過ごす時間を大切にする
- 睡眠をしっかり取る
- 運動やストレッチをする
- 湯船に浸かる
これから紹介する5つは、どれも今日からできる、シンプルな習慣ばかりです。




































































































































































































「最近ちょっとしんどいな…」と感じている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
1.自分の時間を作る
私が実践していた1つ目のセルフケアは、『自分の時間を作ること』です。
保育士の仕事は、朝から晩まで慌ただしく、勤務時間外にも書類や準備など、やることが山ほどあります。
そのため、
なかなか自分の時間を作ることができない…。
毎日バタバタで、気づけば寝る時間…。
と、いう方も多いですよね。




































































































































































































私も保育士として働いていたころは、毎日忙しくて、休みの日でさえ書類や準備に追われていました。
そのうえ、人間関係のストレスも重なり、心も体も本当にしんどい日々を過ごしていたんです。
そんな毎日の中でも、心と体を少しずつ整えるために意識してほしいのが、「自分のための時間」を持つことです。
とはいえ、

































自分の時間を作ることが難しいのに、どんなふうに言われても…。
そう感じる方もいるかもしれません。
ですが、30分〜1時間くらいでできることでも良いです。
・好きな音楽を聴いてリフレッシュする
・コンビニやスーパーでちょっとしたスイーツを買って食べる
・録りためたドラマを1話だけ観る
など、ほんの少しの時間で自分がホッとする時間を作り、自分のストレスを少し軽くしてあげることもとても大切です。




































































































































































































私も、10分だけでも意識的に「自分の時間」を持つようにしたことで、少しずつ気持ちに余裕が生まれてきました。
ほんの少しでも自分の時間を作ることで、4つのメリットを感じることができるはずです。
- 頭の中を一度リセットできる
考えごとから離れ、気持ちを整理しやすくなる - 気分転換になり、翌日を前向きに迎えやすくなる
小さな楽しみが心の切り替えにつながる - 「自分を大事にできた」という満足感が得られる
自分のために過ごした時間が自己肯定感を育てる - ストレスを蓄積しにくくなる
定期的に気持ちをゆるめることで、心に余裕が生まれる
保育士として勤務していると、
「子どもたちのために」
「周りに迷惑をかけないように」
などと考えてしまい、自分のことを後回しにしてしまう方は多いのではないでしょうか。
でも、そんなふうに毎日頑張っているからこそ、“あえて”自分を大切にする時間を、ほんの少しでも作ってあげてください。




































































































































































































そうすることで、ストレスがやわらぎ、心にも少しずつ余裕が生まれてくるはずですよ。
2.心を許せる人と過ごす時間を大切にする
私が実践していた2つ目のセルフケアは、『心を許せる人と過ごす時間を大切にすること』です。
仕事も忙しいし、そんな時間取れないよ?
疲れているから、友人と会ってる余裕なんてない…
もしかしたら、多くの方がこのように感じているのではないでしょうか。




































































































































































































私も保育士のときは、友達と遊ぶ余裕もなく、ひたすら仕事をして、常に疲れていました…。
私のように、毎日の仕事に追われて、誰かとゆっくり過ごす余裕がないという方も多いかもしれません。
ですが、そんなときこそ、「自分の気持ちを安心して出せる相手と過ごす時間」が、心の支えになってくれることも多いです。
皆さんは、心を許せる人と一緒にいると、気を遣わずに話せたり、ただ一緒にいるだけでホッとしたり、安心できたりした経験ありませんか?




































































































































































































私も以前、信頼できる友人とランチに行って、職場のグチを言い合ったり、買い物をしたりするだけで、ずいぶん気持ちが軽くなりました。
だからこそ、「こういう時間って大事だな」って、心から思ったんです。
もちろん、友人と予定を合わせるのが難しいときもあるでしょう。
そんなときは、あらかじめ会う日を決めて楽しみにしておいたり、LINEでちょっと話すだけでも良いと思います。
どうしても誰かと過ごすことが難しい時期には、自分が安心できる場所や習慣(カフェに行く、本を読むなど)を“心の避難所”にしてみるのもおすすめです。




































































































































































































私も会えないときは少し電話をして、愚痴を聞いてもらったり、カフェでゆっくり過ごしてみたりすることもありました。
このように、心を許せる人と過ごす時間には、こんなメリットがあります。
- 安心して本音を話せる
自分を無理に作らなくていいから、心が自然と軽くなる - 気分転換になる
グチをこぼしたり笑ったりすることで、ストレスが和らぐ - 孤独感がやわらぐ
「自分をわかってくれる人がいる」と思えるだけで、気持ちが安定する - 次の予定があるだけで前向きになれる
「楽しみ」があると、毎日を乗り越える小さな原動力になる
人間関係がつらく感じるときこそ、つい誰にも会いたくなくなったり、ひとりで抱え込みがちになります。
でも、そんなときこそ、無理のない範囲で、「今日は少しだけ話してみようかな」と感じたタイミングで、大切な人とつながる時間を作ってみてください。




































































































































































































きっと、気持ちがラクになるはずですよ。
3.睡眠をしっかり取る
私が実践していた3つ目のセルフケアは、『睡眠をしっかり取ること』です。
えっ、寝るだけでストレスが解消できるの?
寝る時間なんてないし、ただ疲れを取るためのものじゃないの?
おそらく、多くの方がこのように感じたのではないでしょうか。
たしかに、忙しい毎日では「ゆっくり寝る」なんて、現実的ではないと感じてしまうかもしれません。




































































































































































































実際、私も毎日忙しかったので、睡眠時間を削ることも多くありました…。
でも実は、睡眠は身体だけでなく、心も一緒に整えてくれる大切な時間なんです。

































心も一緒に整えてくれるって、どういうこと?




































































































































































































社会保険出版社によると、こんなことが書かれていました。
・眠っている間に分泌される「成長ホルモン」には、疲れた体を修復する働きがある
・日中に感じたストレスや考えたことを、脳の中で整理し直す役割もある
=睡眠は心身の休息とメンテナンスのためにある
引用:社会保険出版社




































































































































































































また、睡眠時間が不足している場合についての説明についても、記載がありました。
・メンテナンスも不十分になり、疲れがとれなかったり、学習の効果が低くなったりする
・寝る前に食べ過ぎたり飲み過ぎたりすると、消化・吸収・分解などのために余分な労力を使い、十分に休養がとれない
引用:社会保険出版社
つまり、睡眠をしっかり取ることは、「体を休める」だけでなく、
- 心を落ち着ける
- 頭を整理する
という重要な意味があるということがいえます。




































































































































































































実際、私の友人には「寝たら一回リセットできるから、悩んでてもとりあえず寝る」って人がいます。
最初は「そんな簡単に?」と思っていましたが、しっかり眠れた日は、気持ちの切り替えがうまくいくことも多いと実感するようになりました。
保育の仕事は、冷静な判断や穏やかな対応が求められる仕事です。
だからこそ、ストレスを抱えているときほど「睡眠をしっかり取ること」がとても大切なんです。
今日から、
- 寝る30分前〜スマホを見ないようにする
- あたたかい飲み物で気持ちを落ち着ける
- 心地よい音楽や照明でリラックスする
など、今までよりもほんの少し“睡眠の質”を意識してみてください。
ほんの少しでも眠りの質が上がると、翌日の気持ちがぐっと軽くなるかもしれません。




































































































































































































今の自分にできそうなことから、ひとつだけでも試してみてくださいね。
4.運動やストレッチをする
私が実践していた4つ目のセルフケアは、『運動やストレッチをすること』です。
運動と言われても、
- 苦手意識があるからやりたくない
- 余計疲れてしまいそうで、やりたくない
など、このように感じた方も多いかもしれませんね。




































































































































































































私も昔から運動は苦手なので、極力避けていました。
しかし、ウォーキングなどの軽い運動やストレッチには、心の疲れをやわらげてくれる効果があるんです。

































え?運動って疲れるだけじゃないの?
運動に苦手意識がある方は、どうしてもこのように思ってしまうのは、無理はありません。
しかし、ウォーキングのような軽い運動でも、「セロトニン」や「エンドルフィン」といった、気分を安定させてくれるホルモンが分泌されると言われています。
このホルモンたちが脳に働きかけて、ストレスをやわらげたり、ポジティブな気持ちを引き出してくれるんです。
とはいえ、
- ウォーキングもちょっとハードルが高いんだけど…。
- 天気が悪い日とか、夏場は熱中症のリスクも高いし、運動できないよね…。
など、こんなときは、自宅でも簡単にできるストレッチがおすすめです。




































































































































































































運動、ストレッチを行うことによるそれぞれ期待できることは、下記の通りです。
- 運動によって期待できること
-
- 交感神経が優位になり、前向きな気分を引き出してくれる
- セロトニン・エンドルフィンなどのホルモンで、心が安定しやすくなる
- ストレッチによって期待できること
-
- 緊張した筋肉をゆるめてくれる
- ストレスで乱れた自律神経を整える手助けをしてくれる




































































































































































































私も、寝る前にほんの5分だけストレッチをしていた時期があるのですが、寝つきも改善され、気持ちも少し穏やかに保つことができたように思います。
ストレスを溜め込んでしまうと、
- 寝つきが悪くなる
- 夜中に何度も目が覚める
- 翌日も気分が晴れない
といった悪循環に陥りやすくなってしまいます。
だからこそ、ストレスを感じたときは、無理のない範囲で体を動かしてみましょう。




































































































































































































もちろん、無理に毎日やろうとしなくても大丈夫です。
少しだけ体を動かそうと思ったときに、
- 朝に3分だけストレッチしてみる
- 天気の良い日は1駅分歩いてみる
- 寝る前に深呼吸と軽い肩回しをしてみる
など、こんなちょっとしたことでも、気持ちがふっと軽くなるはずです。




































































































































































































大切なのは、無理せずに少しずつ自分のペースで行うことです。
自分にちょうどいい運動を、ぜひ取り入れてみてくださいね。
5.湯船に浸かる
私が実践していた5つ目のセルフケアは、『湯船に浸かること』です。
「えっ?湯船?毎日シャワーで済ませてるし…」
「そもそも疲れてるのに、お風呂を沸かすのもしんどいんだよね…」
もしかしたら、このように感じた方もいるかもしれませんね。




































































































































































































たしかに、忙しい毎日の中で湯船にお湯を張るのって、少し面倒に感じることもありますよね。
私もついシャワーで済ませがちでした。
でも実は、湯船にしっかり浸かることで、体だけでなく“心”までリラックスできる時間になるんです。

































心までリラックスできる時間になる?
本当にそうなの??
このように不思議に思う方も多いかもしれません。




































































































































































































しかし、湯船に浸かることで心がリラックスする理由は、3つあります。
- 体温が上がることで副交感神経が活性化し、心身がリラックス状態になるから
- 水圧によってマッサージ効果を得ることができるから
- 浮力作用で体全体の緊張がほぐれるから
つまり、ただ温まるだけでなく、身体と心の両方に癒しをもたらしてくれるということなんです。
しかし、

































お湯の温度は、どれくらいがいいの?
あと、湯船に浸かっている時間はどのくらいがいいのかな?
と疑問に思う方もいるかもしれません。
どんなふうに入浴すればリラックス効果が得られるのか、おすすめの方法は、下記の通りです。
- お湯の温度は、38〜40℃くらい
- 時間は、20〜30分ほど
全身浴が苦手な方は、まずは半身浴から始めましょう。




































































































































































































無理なく自分のペースで慣れていけばOKです。
私も、全身浴が苦手なので、半身浴でゆっくり入ることが多くありましたが、驚くほど気持ちがほぐれた経験があります。
さらにおすすめなのが、アロマや入浴剤を活用することです。
香りの力は思っている以上に大きく、自分の好きな香りに包まれることで、自然と気持ちがほぐれやすくなります。
入浴剤やアロマを取り入れることで、バスタイムが「心と体を労わる時間」に変わり、ストレスで張りつめていた気持ちも、少しずつゆるんでいくはずです。

































アロマを使ってみたいけど、詳しくないんだよね…。
はじめてのアロマ選びに迷ったら、『ラサーナ アロマ』がおすすめです。
海藻ヘアエッセンスでおなじみのラサーナから生まれたアロマグッズで、初心者さんにも使いやすく、プレゼントにもぴったりなラインナップが揃っています。




































































































































































































ラサーナ アロマの特徴は、下記の通りです。
- 手軽に始められる超音波式アロマディフューザー
お部屋全体にやさしい香りを広げてくれる、使いやすい定番アイテム - 火も電源も不要なアロマリードディフューザー
天然のリードを使用し、場所を選ばず安心して使えるインテリアにもなる芳香グッズ - 100%天然の香り「エッセンシャルオイル」
ナチュラル派に嬉しい、植物由来の香りでリラックス空間に - 贅沢なバスタイムにぴったりなアロマバスソルト
お風呂で心と体をときほぐしたい日におすすめ - 香りの種類も豊富で選ぶ楽しさも◎
アロマ初心者の方はもちろん、「ちょっとしたご褒美」や「ギフト選び」にも喜ばれている人気アイテムです。




































































































































































































私自身はまだ使ったことがないのですが、調べてみると、香りの種類も豊富で「初心者でも選びやすい」という口コミも多く、ちょっと気になっています。
「今日はちょっと疲れたな…」という日には、こうしたアイテムを取り入れて、心と体をやさしくととのえる時間を作ってみるのもいいかもしれませんね。
初心者さんでも使いやすい『ラサーナ アロマ』が気になる方は、こちらからチェックできます。
▶︎ラサーナ アロマのラインナップを見てみる ![]()




































































































































































































自分へのちょっとしたご褒美に、こうした香りのアイテムを取り入れてみるのもおすすめです。
この章では、実際に保育士として働いた経験がある私が実践していたストレスをやわらげるためのセルフケア法を紹介しました。
- 自分の時間を作る
ほんの10分でも、自分だけの時間を持つことで心に余裕が生まれる - 心を許せる人と過ごす時間を大切にする
安心できる相手と過ごすことで、心の緊張がほぐれやすくなる - 睡眠をしっかり取る
質の良い睡眠が、心と体のメンテナンスにつながる - 運動やストレッチをする
軽い運動やストレッチが、心を前向きに整えてくれる - 湯船に浸かる
あたたかいお湯が、心も体もじんわりとゆるめてくれる
保育士という仕事に全力で向き合っている方ほど、自分のことはついつい後回しになりがちです。
だからこそ、自分に合ったセルフケア方法を見つけ、ストレスを軽くする必要があります。




































































































































































































それは、絶対に避けなければいけません。
そして、今回紹介した5つのセルフケアは、どれも特別な準備やスキルがいらず、日々の生活にやさしく取り入れられるものばかりです。

































ちょっと疲れてるかも…
このように感じたときは、お伝えした方法もしくは、自分に合った方法で自分自身をいたわる時間を少しでも持ってあげてください。
そうすることで、ストレスを少し減らすことができるはずです。




































































































































































































あなた自身を大切にすること、それが一番のケアになりますよ。
放置すると危険!人間関係が最悪なまま働き続ける6つのリスク


「職場の人間関係がつらい…でも、今すぐ辞めるわけにもいかないし…」
「もう少し頑張れば、そのうち状況がよくなるかもしれない…」
そう思いながら、我慢して働き続けていませんか?
たしかに、すぐに辞める決断をするのは勇気がいりますし、「ここで投げ出したらダメだ」と自分に言い聞かせている方もいるかもしれません。
ですが、人間関係の悪い職場で我慢を続けていると、少しずつ心や体に影響が出てくることがあります。




































































































































































































私自身も、以前は「もうちょっと耐えればなんとかなる」と思って踏ん張っていました。
でも、気づいたときには、心に余裕がなくなっていて、笑顔を向けることさえしんどくなっていました。
それほどまでに、人間関係のストレスは想像以上に大きな負担になるものです。
保育の現場は閉鎖的な空間で、逃げ場が少ないぶん、人間関係が悪化するとその影響がより深刻になりやすいんです。




































































































































































































だからこそ、「今のままで本当に大丈夫かな…?」と一度立ち止まって、自分の状態を見つめなおすことが大切だと感じています。
この章では、人間関係が最悪なまま働き続けることで起こりやすい6つのリスクについてお伝えします。
- 人間関係に疲れてしまう
- ミスが続いてしまう
- 悩み抱え込んでしまう
- 良い保育をすることができなくなる
- 保育士の仕事から離れたいと感じる
- 精神疾患になるリスクも高まる
あなた自身の心と体を守るためにも、

































あ、今の自分にあてはまるかも…
と感じたことがあれば、ちょっと黄色信号かもしれません。




































































































































































































そんなときは、まず「自分がどんな状態にいるのか」を知ることから始めてみましょう。
では、実際に起こりうる7つのリスクについて、私の経験も交えてお話ししていきますね。
1.人間関係に疲れてしまう
保育士として働く中で、最も消耗しやすいのが『人間関係のストレス』です。
「保育士同士の関係がギスギスしている…」
「いつも気を張っていて、正直もう疲れた…」
こう感じたことがある方も、多いのではないでしょうか?
保育士の仕事は、
- 子どもたちが安心して過ごせる環境をつくること
- 保護者が安心して子どもを預けることができること
- 子ども・保護者・職員が信頼関係を築けること




































































































































































































この3つがうまく保たれていると、子どもも保護者も職員も、みんなが安心して過ごせる環境になりますよね。
そのためには、保育士同士が協力しながら保育を行うことが理想ですが、残念ながら現場ではうまくいかないことも少なくありません。
たとえば、
- クラス内の雰囲気が悪くて話しかけづらい
- 先輩保育士の言い方がきつくて毎日ビクビクしている
- 「空気を悪くしないように」と、常に気を遣っている
このような状態が続くと、笑顔でいることさえつらくなってしまうことがあります。




































































































































































































私も、子どもとの関わりよりも、保育士同士の人間関係に気を取られてしまい、「仕事に行くのがしんどいな…」と思う日も、正直ありました。
ですが、本来であれば、子どもの成長を見守ったり、一緒に喜び合ったりと、子どもと向き合う時間のはずです。
それにも関わらず、保育士同士の人間関係に疲れ切ってしまうと、その余裕すらなくなってしまうリスクが高まります。
だからこそ、

































ちょっとしんどいな…
と感じたときは、我慢しすぎず、自分の心の状態を見つめることも大切です。




































































































































































































まずは深呼吸をして、「大丈夫かな?」と自分に問いかけてみてくださいね。
2.ミスが続いてしまう
人間関係のストレスが続く職場では、思いがけず「ちょっとしたミス」が増えてしまうことがあります。
「また確認し忘れてしまった…」
「さっきのやりとり、ちゃんと伝わってたかな…」
こんなふうに、小さなミスが続いてしまった経験はありませんか?




































































































































































































私も、立て続けにミスをしてしまったことがあります。
そのたびに「またやっちゃった…」と落ち込み、反省ばかりしていました。
ですが、実はこの悩み、保育士として働く中ではめずらしいことではありません。
たとえば、いつも周囲の空気を気にしながら仕事をしていると、本来集中すべきことに意識が向けられず、うっかり確認を飛ばしてしまったり、判断が遅れてしまったりすることがあります。




































































































































































































私が以前勤めていた保育園でも、クラス内の保育士同士の人間関係が悪く、なんとなく常にピリピリしていた空気でした。
そんな中で働いていた私は、どうしても
- 周囲の顔色が気になってしまい、心が落ち着かない
- 子どもの荷物を取り間違える
- 子どもへの声かけが遅れてトラブル対応が後手になってしまう
など、ちょっとしたことが重なって、ミスが増えてしまったんです。




































































































































































































ミスをしたときに、「どうすればよかったのかな…」と考えるのと同時に、自分の仕事のミスの多さに落ち込み、自分を責めてしまってばかりでした。
もちろん、ミスをすれば先輩保育士から注意されます。
ただ、先輩保育士から強い口調で指摘されることが多く、そのたびに自信を失っていきました。
「このままではいけない!頑張らないと…!」
「叱られないようにしなきゃ…」
そんなふうに気持ちだけが焦ってしまい、さらにミスをしてしまうことも多くなっていったんです。




































































































































































































その当時の私は、完全に悪循環に陥ってしまっていました。
そして、子どもたちにしっかり向き合う心の余裕も、次第になくなっていったんです。
子どもとの関わりだけでなく、職員同士の関係も、無理をして頑張りすぎると空回りしてしまうものです。
もし最近、

































ちょっとミスが増えてきたかも…?
と感じているなら、もしかすると人間関係のストレスが影響しているかもしれません。
まずは、自分が何に一番疲れているのか、そっと見つめてみてください。




































































































































































































そこに気づけるだけでも、少し気持ちがラクになることがありますよ。
ミスを責めるのではなく、「今の自分はちょっと頑張りすぎてるのかも」と優しく気づいてあげることも、心を守る一歩です。
3.悩みを抱え込んでしまう
人間関係がうまくいっていない職場では、「誰にも相談できない…」という状況に陥ってしまうことがあります。
保育士の仕事では、
- 子どもへの対応
- 保育のやり方
- 保護者への対応
など、さまざまな悩みに直面します。
私も、
「ちゃんと子どもたち一人ひとりと向き合うことができているだろうか…?」
「自分の保育・保護者への対応は、これで合っているんだろうか…?」
「どうすれば、先輩みたいにスムーズに保育することができるんだろう…?」




































































































































































































と、不安になったり、悩んだりして、自信が持てないことが多くありました。
しかし、先輩保育士との関係がうまくいっていなかったので、
「声をかけること自体が怖い」
「そんなことも分からないの?」
「自分で考えてよ」




































































































































































































など、思ってしまい、相談したくても、相談することもできず、1人で悩みを抱え込んでしまったんです。
その結果、不安や焦りがどんどん大きくなり、
- 食欲も落ちた
- 寝つきが悪くなった
- 途中で目が覚める
など、体調面にも影響が出てきてしまいました。




































































































































































































体調面に影響が出てきたときには、「このまま続けられるのかな…」とすら思ってしまったほどです。
本来であれば、一緒に働く仲間同士、悩みを共有し、アドバイスをもらえる関係が理想です。
しかし、人間関係が悪いとその雰囲気すらなくなり、「相談する」ことが怖くなってしまいます。




































































































































































































だからこそ、人間関係が最悪な職場では、「悩みを抱え込んでしまう」というリスクが高くなってしまうというわけです。
一人で悩みを抱え続けることは、心と体に大きな負担をかけます。
もし、今
「最近、誰にも相談できていないな…」
「体も心もしんどいな」
そんなふうに感じたときは、無理をする前に、いまの自分の気持ちにそっと目を向けてみてください。




































































































































































































「つらい」「苦しい」と思うのは、頑張ってきた証拠です。
どうかその気持ちを否定せず、認めてあげてくださいね。
4.良い保育をすることができなくなる
人間関係がうまくいっていない職場では、「子どもたちに笑顔を向けることすらつらい…」と感じてしまうことがあります。
子ども一人ひとりの気持ちに寄り添い、成長を支えるために、日々たくさんの関わりや声かけを重ねていくことが大切です。
しかし、人間関係が悪化していると、
- 保育士同士の連携がうまくいかない
- 職場の空気がギスギスしている
といった状態となり、「子どもと向き合う余裕」がなくなってしまうことがあります。




































































































































































































実際、私が働いていた保育園でも保育士同士の対立があり、常にピリピリした雰囲気でした。
必要最低限の会話だけで、笑顔で話せるような空気ではなかったんです。
このような状態で保育をしていても、
- 子どもたちの笑顔を見ても、うまく反応できない
- 必要なタイミングで適切な声かけができなくなる
- 子どもの些細な変化に気づきにくくなる
など、本来大切にしたい「子どもとの関わり」が、どんどん遠ざかっていくような感覚になり、「良い保育って、なんだろう…?」とすら分からなくなってしまいました。
このように、人間関係の悪化は、保育士自身の気力や判断力を奪い、結果として“良い保育ができない状態”を引き起こしてしまいます。
もし最近、

































子どもと向き合う余裕がない…。
と感じているなら、それは人間関係の影響かもしれません。




































































































































































































あなたが感じている“つらさ”には、ちゃんと理由があるはずです。
どうか、その声に耳を傾けてあげてくださいね。
5.保育士の仕事から離れたいと感じる
保育士の仕事は、楽しいし、やりがいを感じるけれど、
「このまま保育士を続けていて、私は本当に幸せなのかな…?」
「なんだか最近、仕事に行くのがつらいかも…」
このように感じたことはありませんか?




































































































































































































実は私も、保育士同士の人間関係に悩んだり、業務の負担が重なったことで、同じような気持ちになったことがあります。
保育士の仕事は、書類作成や行事の準備など、やるべきことがたくさんあります。
そのため、体力的にも精神的にも負担が大きく、決して楽な仕事ではありません。
それでも、職場の人間関係が良好であれば、
「子どもの成長を見守れるのが楽しい」
「やりがいを感じながら働けている」
と、前向きな気持ちで頑張れる場面も多いはずです。




































































































































































































私自身も人間関係が良かった職場では、毎日の保育が本当に楽しくて、「また明日も頑張ろう」と自然に思えていたんです。
子どもたちの笑顔に癒されながら、保育士として充実した日々を過ごしていました。
しかし、その環境が少しでも崩れると、
- 「どうして、こんなに気を遣ってばかりなんだろう…」
- 「子どもと関わる以前に、保育士同士の関係がつらくて行きたくない…」
と、感じてしまいやすくなるので、状況は一変します。




































































































































































































私も、保育士同士の人間関係が悪化したときは、上記のことを思いながら出勤したこともあります。
クラス内では、陰口や悪口を聞くことも多くあったため、「もしかして自分も言われているかも…」と、常に不安な気持ちでいっぱいでした。
そんな状態では、子どもたちとしっかり向き合う余裕もなくなるため、
- 淡々と業務をこなすだけの日々になってしまう
- 「本当にやりたい保育ができているのかな…?」と疑問を感じるようになる
など、保育士としての仕事にも、次第に影響が出てきます。




































































































































































































このような状態では、質の良い保育の提供は難しいですよね。
そのため、「こんなに人間関係がうまくいかないなら、保育士を辞めて、もっと落ち着いた環境で働いた方がいいかもしれない…」と感じるようになってしまったんです。
もちろん、どんな仕事にも大変なことはあります。
たとえ、「子どもが好き」という気持ちがあっても、どうしても乗り越えられない職場環境は存在します。
だからこそ、

































もうこの仕事を続けるのはつらいかも…。
と感じるあなたの気持ちも、決して間違いではありません。




































































































































































































無理を続けて心が壊れてしまう前に、「離れる」という選択肢があってもいいと、私は思います。
大切なのは、自分の気持ちに正直になり、自分を守ってあげることです。




































































































































































































どうか、その気持ちを我慢しすぎず、大切にしてあげてくださいね。
6.精神疾患になるリスクも高まる
体調は悪くないはずなのに、
「最近ずっと気が重い…。」
「なんとなく元気が出ない…。」
「もう、仕事のことを考えるだけで胃がキリキリする…。」
そんなふうに感じる日が続いていませんか?
もちろん、
- 疲れが溜まっていて、元気が出ない日
- 仕事のプレッシャーを感じ、気が重くなる日
といったことは、誰にでもあるものです。




































































































































































































ですが、こうした状態が何日も続いている場合は、少し注意が必要かもしれません。
保育士として働き続けるためには、
- やりがいを感じられるかどうか
- 人間関係は良好か
- 労働環境は整っているか
この3つのバランスがとても大切です。
しかし、これらのバランスが崩れてしまうと、少しずつ心や体に負担がかかってしまうのです。




































































































































































































私自身も、この3つのうちのひとつ”保育士同士の人間関係”が原因で、本当につらいと感じたことがありました。
具体的には、下記のようなことです。
- 先輩保育士の厳しい言い方に毎日ビクビクしてしまう
- 陰口を言われているのではないかと不安になる
- 誰にも相談できないまま悩みを抱え込み、どんどん気持ちが沈んでいく
こうした日々が続いた結果、
- 朝、布団から起き上がるのがつらく、食欲もない
- 疲れが取れず、何もしたくなくなる
- 突然不安に襲われ、涙が止まらなくなる
そんな状態が続いたため、心療内科を受診したところ「適応障害」と診断されました。




































































































































































































当時の私は、「これくらいで病気になるなんて、自分は弱い証拠だ」と、自分を責めてしまいました。
でも今は、はっきりと言えます。
精神疾患は、
- 誰にでも起こりうるもの
- そして、それは決して「弱さ」ではない




































































































































































































むしろ、「よくここまで頑張ったね。もう無理しなくていいよ」と、身体が出してくれた大切なサインだったのだと思います。
もし今、
「つらいな…」
「もう限界かも…」
と感じている方がいたら、
- 信頼できる誰かに相談する
- 専門機関の力を借りる
といった行動を、どうかためらわないでください。
これは「逃げ」ではなく、「自分を守るための大切な行動」です。




































































































































































































あなたの心と体は、何よりも大切なものです。
無理をしすぎず、自分の気持ちに耳を傾けてあげてくださいね。
この章では、保育士として働いた経験のある私が、実際に人間関係の悪化によって感じた“6つのリスク”についてお伝えしました。
- 人間関係に疲れてしまう
子どもと関わるよりも、職員同士の空気ばかりを気にしてしまうようになる - ミスが続いてしまう
焦りや緊張から判断力が鈍り、確認不足や声かけの遅れが増えていく可能性がある - 悩み抱え込んでしまう
「相談するのが怖い」と感じ、ひとりで悩み続けてしまいやすくなる - 良い保育をすることができなくなる
気持ちの余裕がなくなり、子どもとの関わりさえ負担に感じてしまう - 保育士の仕事から離れたいと感じる
子どもが好き」な気持ちがあっても、職場環境のつらさで気持ちが折れてしまう - 精神疾患になるリスクも高まる
心のサインを見逃し続けると、限界を超えてしまう




































































































































































































これらはすべて、私自身が実際に経験したことでもあります。
私の場合は、「ちょっとつらいな…」と思う日が続いていたのに、見て見ぬふりをしてしまったことで、心と体の不調へとつながってしまいました。
もちろん、保育士という仕事の中で、悩みや葛藤を抱えるのは自然なことです。
今、

































この中のどれか、自分にあてはまっているな…




































































































































































































このように感じた方は、自分の心と体の声に、そっと耳を傾けてみてくださいね。
自分を大切にすることは、決してわがままなんかではありません。
あなたが、心から笑顔で保育に向き合えるようにするためにも、まずは自分の状態に気づいてあげることから、はじめてみてください。




































































































































































































そうすることで、自分を守りつつ、笑顔で子どもたちと過ごすことができるはずです。
保育士の人間関係が改善しないなら、転職という選択肢もアリ!


現在働いている職場で、「人間関係をなんとか良くしたい」と少しずつ努力を重ねてきたものの、なかなか状況が変わらず、疲れきってしまっていませんか?
「どうしたら人間関係を改善できるのかわからない…」
「もう限界かもしれない…」
そんなふうに思い悩み、心が限界に近づいている方もいるのではないでしょうか。
本当は「今すぐ辞めてしまいたい」と思っているのに、
- 「甘えていると思われたらどうしよう…」
- 「あともう少し頑張れば、きっと良くなるかもしれない…」
と、自分を奮い立たせて、なんとか踏みとどまっている方ほど、実はとても追い込まれていることが多いんです。




































































































































































































私自身も、同じように人間関係の悩みを抱えて転職を繰り返してきたうちのひとりです。
そのたびに、「また辞めてしまった…」と落ち込んで、自分を責めてしまうこともありました。
私の場合、
- どうしても周りの人の目が気になってしまう
- わからないことや困っていることをうまく伝えられない
- 良かれと思って取り組んだことが、空回り
といったことが重なり、一人で悩みを抱え込んでしまっていました。




































































































































































































仕事中もずっとそのことが頭から離れず、集中できない日々が続いていたのです。
さらに、保育士同士の人間関係は非常に複雑で、クラス内には派閥のようなものができており、安心して保育に取り組めるような雰囲気とは程遠い状況だったんです。
「それでも辞めずに頑張らなきゃ」と踏ん張っていたものの、最終的には心身ともに限界を迎え、退職を選ばざるを得なくなりました。




































































































































































































今でもその当時のことを思い出すと、「本当に辛かったな…」と思ってしまうことがあります。
そんな経験をしたからこそ、辞めることは決して逃げではないと、はっきりと言えるんです。
そうなる前に、自分のメンタルの変化に気づいてあげることも大切です。




































































































































































































たとえばこちらの記事では、保育士が心をすり減らしてしまう原因や対策について詳しく解説しています。
心が限界を迎える前に気づくためにも、参考になるかもしれません。
もし、

































もう保育士という仕事自体が自分には合っていないのかも…
と感じているなら、異業種への転職を考えてみるのもひとつです。




































































































































































































私も、今は保育士を離れ、接客業のパートをしています。
異業種転職を視野に入れたい方は、こちらの記事も参考になりますよ。
しかし、中には、

































自分が辞めたらまわらなくなるのでは…?
と罪悪感を抱えてしまっている方もいるかもしれません。
でも、本来は職場の運営体制に問題があるケースも少なくないのです。




































































































































































































そんなふうに「職場がまわらないのは自分のせい」と思い込んでしまいがちな方には、一人休むと回らない職場の構造や、辞めてもいい理由について解説したこちらの記事もおすすめです。
それでも、
- 「退職の意志を伝えるのが怖い」
- 「うまく切り出せない…」
という方もいるかもしれません。
そうしたときのために、退職代行サービスという手段もあります。




































































































































































































「でも退職代行ってどこまでやってくれるの?」と不安な方に向けて、利用の流れやメリット・注意点をまとめた記事もあるので、ぜひ参考にしてみてください。
辞めることは、決して逃げではありません。
それは、退職は“自分の心と体を守るための前向きな選択肢のひとつ”です。
人間関係がどうしても改善されない職場に、無理をして居続ける必要はありません。




































































































































































































たまたま、今の働く環境があなたに合っていないだけで、あなたがダメなわけではないのです。
実際、保育士の現場は園によって雰囲気が大きく異なります。
だからこそ、「今の環境を変える」ということが、心の負担を軽くする第一歩になることもあります。
もし今、

































転職を少しでも考えているけど、どう動いたらいいのかわからない
このように感じている方は、保育士専門の転職エージェントを活用してみるのもひとつの方法です。




































































































































































































私も転職エージェントを利用し、人間関係が良好な職場に転職することができました。
この後は、私も実際に利用したことがある転職サービスをはじめ、人間関係の悩みに理解のあるサポートが受けられる転職サービスを紹介します。




































































































































































































あなたに合った職場を見つけるヒントになるかもしれませんので、ぜひチェックしてみてくださいね。
保育士に特化したおすすめ転職エージェント


「人間関係がつらくて、もう限界かも…」
「保育の仕事は好き。でも、職場の人間関係に疲れてしまった…」
「違う保育園への転職も考えたいけど、どこに相談すればいいのかわからない…」
こんなふうに悩んでいる方は、あなただけではありません。




































































































































































































私も人間関係に悩んで転職をくり返していましたが、結局どの職場でも同じように悩み、自分に合う職場がわからなくなってしまいました。
そんな私が最後に頼ったのが、「保育士専門の転職エージェント」でした。
保育士に特化した転職エージェントは、ただ求人を紹介してくれるだけではありません。
求職者一人ひとりの、
「人間関係が良好な職場を選びたい」
「自分の希望、ライフスタイルに合った働き方がしたい」
そんな気持ちにも丁寧に寄り添いながら、希望に合う職場を一緒に探してくれます。
とはいえ、保育士向けの転職エージェントはたくさんあるため、

































どのサービスを選べばいいの?
と迷ってしまいますよね。




































































































































































































実際に、私もいくつかのサービスを比較しながら悩んだ経験があります。
そこでこの章では、人間関係の悩みにもしっかり配慮した求人を取り扱っている、保育士に特化したおすすめの転職エージェントを5つ紹介します。
いずれも、保育士に特化しており、それぞれに異なる強みがあります。




































































































































































































あなたの状況や希望に合った選択ができるように、詳しくお伝えしていきますね。
1.保育のお仕事
保育士に特化したおすすめ転職エージェントの1つ目は、『保育のお仕事』です。




































































































































































































『保育のお仕事』の特徴は3つあります。
- 求人数が圧倒的に多い(約50,000件)
他社の転職エージェントが数百件〜2万件ほどなのに対して、『保育のお仕事』では約5万件の求人を保有している - 多様な施設の求人を取り扱っている
認可保育園はもちろん、企業内保育・病院内保育・小規模保育・学童保育など、さまざまな施設形態の求人をカバーしている - サポート体制が充実している
面接の日程調整
面接前のアドバイス
面接の同行
合否の連絡
退職手続き(在職中の場合)
引用:保育のお仕事
また、保育のお仕事では、会員登録後にしか見られない「非公開求人」も多く、条件の良い職場と出会える可能性が広がります。




































































































































































































こうした特徴から、以下のような方にぴったりのサービスです。
- 一度にたくさんの求人をみて比較したい方
- 認可保育所以外の求人もみたい方
- 初めて転職する方
- 転職エージェントの利用が初めてで不安な方




































































































































































































実は私も『保育のお仕事』を利用したことがあります。
会員登録後のヒアリングでは、
- 以前の職場で人間関係に悩み、転職をくり返していたこと
- できるだけ人間関係が落ち着いている職場で働きたいこと
この2つを中心に希望を伝えました。
すると、担当の方が丁寧に話を聞いてくださり、比較的人間関係が良好な保育園をいくつか紹介してくれたんです。




































































































































































































実際に転職した園では、保育士同士の雰囲気も穏やかで、人間関係に悩むことなく働くことができました。
そのため、「保育のお仕事を利用して本当によかった」と感じたことを、今でもよく覚えています。
こうした経験からも、人間関係で悩んでいる方にとって、『保育のお仕事』は心強い選択肢のひとつだと自信をもっておすすめできます。




































































































































































































私自身の体験も踏まえて、『保育のお仕事』の口コミ・評判を詳しく解説した記事があります。


実際に利用してみたいと思った方は、事前に評判をチェックしておくのもおすすめです。




































































































































































































保育のお仕事が気になる方、ぜひ合わせて読んでみてくださいね。
\ 実際に使ってみてよかったサービスです!/
2.保育専門求人サイトほいく畑 
保育士に特化したおすすめ転職エージェントの2つ目は、『保育専門求人サイトほいく畑』です。




































































































































































































『ほいく畑』の特徴は3つあります。
- 厚生労働大臣認可の信頼できるサービス
『ほいく畑』は、厚生労働大臣から認可を受けた就業支援サービス - 未経験・ブランクOKの求人が豊富
関東・関西・東海・中国・九州の5エリアに対応し、地域に根ざした求人が充実
保育士資格はあるけれど実務経験がない方や、ブランクが長くて不安な方でも応募しやすいのが特長 - 働き方を自由に選べる
『ほいく畑』では、”正社員・パート”だけでなく派遣保育士として働くことも可能 - 日払い対応の給与サービスがある
働いた分をすぐに受け取れる「給与日払いサービス」があるのも大きな特徴のひとつ
このように『ほいく畑』は、サポート体制が充実しており、未経験・ブランクがある方でも安心して保育の仕事にチャレンジできる環境が整っています。




































































































































































































以上のことを踏まえると、ほいく畑は、下記のような方におすすめです!
- 保育士資格はあるけれど、現場経験がなくて不安な方や、ブランクがあり復帰に迷いがある方
- 派遣や紹介予定派遣など、柔軟な働き方を希望している方
- 給与日払い対応の求人を探していて、急な出費にも対応できる働き方をしたい方
- 転職が初めて、または不安があり、信頼できるコーディネーターのサポートを受けながら進めたい方
- 地元や希望の地域に特化した求人を探し、自分に合う職場で納得のいく働き方をしたい方




































































































































































































私は『ほいく畑』を利用したことはありませんが、現在、保育士を離れて10年が経ちました。
今あらためて現場復帰を考えるなら、未経験・ブランク歓迎の求人が多い『ほいく畑』は、安心して使えるサービスだと感じます。
経験に不安がある方や、自分に合う働き方を探したい方は、一度『ほいく畑』をチェックしてみてはいかがでしょうか。
\ 安心のサポートと柔軟な働き方が魅力!/
3. レバウェル保育士
レバウェル保育士
保育士に特化したおすすめ転職エージェントの3つ目は、『レバウェル保育士』です。




































































































































































































『レバウェル保育士』の特徴は4つあります。
- 専門アドバイザーによる丁寧なサポート
保育業界に精通した専任アドバイザーが、転職相談から内定後のフォローまで徹底的にサポート - 職場のリアルな情報がわかる
年間4,000件以上の施設訪問や、派遣スタッフからのフィードバックを通じて、現場の雰囲気や人間関係といった“リアルな職場情報”を提供 - 応募から転職までスムーズ
LINEや電話でのやり取りに対応しており、自分のペースで転職活動を進められる - 短期転職に強い
6ヶ月以内の転職希望者を積極的に支援しており、スピード感のあるサポート体制も魅力
ミスマッチな職場に入る不安がある方にとって、現場の“リアル”をふまえて求人提案してくれるレバウェル保育士は、安心して相談できるサービスといえるでしょう。




































































































































































































上記の特徴を踏まえると、レバウェル保育士は、下記のような方におすすめです!
- 転職に不安があり、信頼できるプロにサポートしてほしい方
- 忙しくて転職活動の時間が取りにくい方(LINEでの相談が可能)
- 自分に合った職場環境(人間関係・雰囲気)を重視したい方
- 好条件・非公開求人に出会いたい方
- 6ヶ月以内に転職したいと考えている方




































































































































































































私は『レバウェル保育士』を利用したことはありませんが、職場の“リアル”まで把握した上で提案してくれる点はとても魅力的だと感じます。
特に、
- 「職場の人間関係が不安…」
- 「ミスマッチな職場には入りたくない」
という方にとっては、レバウェル保育士のように現場情報に強いサービスは、安心して相談できる存在になるのではないでしょうか。




































































































































































































そんな不安を抱えている方にこそ、レバウェル保育士のような“リアルな情報をもとに提案してくれる”サービスは、心強い味方になるはずです。
\リアルな情報と手厚いサポートで転職を後押し! /
4.保育エイド
保育士に特化したおすすめ転職エージェントの4つ目は、『保育エイド ![]() 』です。
』です。




































































































































































































『保育エイド』の特徴は3つあります。
- 人間関係の良好な職場のみを厳選
保育エイドでは、現場の雰囲気や人間関係に配慮し、働きやすいと感じられる職場のみを厳選して紹介している - 元保育士のコーディネーターが対応
実際に保育現場を経験したスタッフが、転職の不安や悩みに寄り添いながらサポートしてくれる - 一人のコーディネーターが企業・求職者の両方を担当
企業側と求職者側の両方を一人のコーディネーターが担当することで、希望条件と職場のニーズをしっかり把握し、ミスマッチの少ない紹介ができる体制を整えている
『保育エイド』は、保育士の退職理由の多くを占める「人間関係の悩み」に注目し、働く前に“どんな職場か”をできるだけ詳しく伝えることで、ミスマッチを未然に防ぐ工夫がされています。




































































































































































































職場の雰囲気や人間関係を重視して転職活動をしたい方にとって、非常に頼れる存在ですよね。
上記の特徴を踏まえると、保育エイドは、下記のような方におすすめです!
- 人間関係が理由で職場を変えたいと考えている方
- 職場の雰囲気や人間関係を重視して転職したい方
- 保育士の資格を持っていて、現場復帰を目指している方
- 初めての転職で、共感してくれるコーディネーターに相談したい方
「人間関係の悩みをなくしたい」
「安心して働ける園を選びたい」
このように思っている方にとって、保育エイドはぴったりのサービスです。




































































































































































































ですが、注意しておきたい点もあります。
- 対応エリアが関東に限定されている
(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県) - 求人はすべて非公開
登録しないと具体的な情報を確認できない
保育士としての転職で最も気になる「職場の人間関係」に注目して求人を紹介してくれる点は、とても魅力的ですが、対応地域が限定なことは、少し残念なポイントかもしれません。
しかし、対応エリアが合う方にとっては、人間関係の悩みを軽くしながら転職活動ができる、非常に心強いパートナーになるはずです。




































































































































































































少しでも気になった方は、まずは公式サイトをのぞいてみてくださいね。
\人間関係の悩みから解放されたいあなたへ /
5.保育バランス
保育士に特化したおすすめ転職エージェントの5つ目は、『保育バランス』です。




































































































































































































『保育バランス』をおすすめする理由は、2つあります。
- 企業内・病院内保育所に特化した小規模保育
企業内保育所や病院内保育所など、小規模で落ち着いた環境に特化した求人を多く扱っている
定員が少ないため、一人ひとりの子どもとじっくり関わる保育ができ、保育士同士の関係性も比較的シンプルなのが特徴 - プライベートを大切にできる働き方
取り扱う求人の多くが「土日休み」「残業なし」「行事なし」など、働きやすさに配慮された内容となっている
仕事とプライベートのバランスを大切にしたい方にはぴったり
このように『保育バランス』は、認可保育園よりも定員数が少なく、比較的穏やかな職場環境が整いやすいのが魅力です。




































































































































































































そのため、以下のような方にとっては、まさにぴったりのサービスだといえます。
- 大人数の保育に疲れてしまった方
- 小規模な環境で、子どもとじっくり関わりたい方
- 土日休みや残業なしの働き方を希望している方
- 人間関係がシンプルな職場でストレスを減らしたい方
「保育は好きだけど、忙しすぎる職場には戻りたくない」
「今度は、心にゆとりをもって働ける環境を選びたい」
そんなふうに感じている方にとって、『保育バランス』は理想的な選択肢になるはずです。




































































































































































































とはいえ、利用するうえで気をつけておきたい点もあります。
- 取り扱っている求人の地域が限定されている
(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県) - 求人はすべて非公開のため、登録しないと詳細が確認できない
保育バランスと同様に、対応地域が限られている点は、地方にお住まいの方にとってはデメリットに感じられるかもしれません。
ですが、対応エリアが合う方にとっては、「小規模×働きやすさ×シンプルな人間関係」がそろった理想的な職場を見つけやすい、非常に魅力的なサービスといえるでしょう。




































































































































































































『保育バランス』の口コミや利用メリットをもっと詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。




































































































































































































少しでも気になった方は、まずは公式サイトをチェックしてみてくださいね。
公式サイトで職場の雰囲気をチェック!
この章では、保育士として働いた経験のある私が、実際に利用・調査した「人間関係に悩む保育士におすすめの転職エージェント」についてお伝えしました。
| ほいく畑
| 保育エイド
| 保育バランス
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対応地域 | 全国 | 全国 (地域により差あり) | 全国 (都市部中心) | 1都3県 ・東京都 ・神奈川県 ・埼玉県 ・千葉県 | 1都3県 ・東京都 ・神奈川県 ・埼玉県 ・千葉県 |
| 求人数 | 約50,000件 | 約4,000件 (このほか、非公開求人あり) | 非公開 | 非公開 | 常時300〜350件 |
| 施設形態 | ・認可保育園 ・企業内保育 ・病院内保育 ・小規模保育 ・学童保育 | ・認可保育園 ・院内保育 ・企業内保育 小規模保育 など | ・認可保育園 ・認定こども園 ・小規模保育 など | 非公開 | ・企業内保育 ・病院内保育 |
| おすすめできる方 | ・一度にたくさんの求人をみて比較したい ・認可保育所以外の求人もみたい方 ・初めて転職する方 ・転職エージェントの利用が初めて | ・未経験・ブランクありでも安心して相談したい方 ・派遣やパートなど柔軟な働き方をしたい方 | ・丁寧なヒアリングで希望をしっかり聞いてほしい方 ・事前に職場の雰囲気まで知っておきたい方 | ・人間関係を1番優先させたい方 ・1都3県にお住まいの方 | ・子ども・保育士の人数が少ない環境で働きたい方 ・仕事もプライベートも充実させたい方・1都3県にお住まいの方 |
| ほいく畑 | レバウェル保育士 | 保育エイド | 保育バランス |
転職エージェントの力を借りなくても、転職することは可能です。
しかし、保育園の雰囲気が掴みきれず、入職してから
「こんなはずじゃなかった…。」
「入職したばかりだけど、もう辞めたい…」
ということもあるかもしれません。
ですが、転職エージェントを活用することで、自分ひとりでは見つけにくい「理想の職場」と出会えるチャンスが広がります。




































































































































































































また、転職エージェントを使うことで得られるのは、求人の紹介だけではありません。
具体的には、以下のようなメリットがあります。
- 事前に職場の雰囲気や人間関係など“リアルな情報”を知ることができる
- 転職後のミスマッチを防ぐサポートが受けられる
- 不安や迷いを相談することで気持ちが軽くなる
- 条件だけではわからない「相性」まで考慮してもらえる
- 日程調整ややりとりなどの負担を減らすことができる
こうしたサポートがあるからこそ、
- 人間関係に悩んでいる
- 忙しすぎる毎日を変えたい
と思っている方には、相談するだけでも心が軽くなるかもしれません。
現在、

































今の職場は自分に合っていないかも…。
と感じているなら、無理にがんばり続けるよりも、視野を広げて“別の選択肢”を考えてみるのも、ひとつの方法です。




































































































































































































たとえば、転職もそのひとつかもしれません。
もちろん、保育士の仕事は、決してラクではありませんが、「自分に合った環境で働くこと」はとても大切なことです。
心のゆとりが持てる場所で、あなたらしく子どもたちと関われる毎日を、少しずつ取り戻していきましょう。




































































































































































































あなたがこれから先、自分にとってちょうどいいバランスで働ける環境と出会えることを、心から願っています。
保育士の人間関係、本当に最悪?実際にあったトラブル14選を元保育士が解説!


「保育士の人間関係って、想像以上に大変なんだって聞いたことがあるけど、具体的に何がそんなに難しいんだろう?」
このような疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?




































































































































































































ここでは、元保育士の私が実際に経験した、保育士の人間関係の悩みを14個にまとめました。
- 閉鎖的な空間
- 業務の負担に偏りがある
- 職員同士を比較する
- 職員を差別する
- 先輩保育士の言い方がきつい
- 先輩保育士のあたりが強い
- 相手の気持ちを考えられない
- 先輩保育士の指導方法が自分に合っていない
- 保育観が合わない
- 悪口をいう
- 大変な仕事を押し付ける
- 自分のミスを認めたくない
- 自分の価値観を押し付ける
- 連絡事項を伝えない




































































































































































































これらの原因と対策を知って、あなたも安心して保育の仕事に打ち込めるように、一緒に考えていきましょう。
1.閉鎖的な空間
保育士の人間関係が最悪になりやすい1つ目の理由は、『閉鎖的な空間なこと』です。
多くの保育園では、年齢ごとに部屋が区切られ、その年齢に適した遊び・学びができるように配慮されています。




































































































































































































日中はクラス単位で、朝夕は合同保育を行うことが多いです。
そのため、同じクラスの保育士と1つの部屋で長時間一緒に過ごすことになるため、
- 保育士同士の人間関係が密接になること
- 閉鎖的な空間になること
など、避けることができません。




































































































































































































人間関係が近すぎてしまうからこそ、トラブルを抱えやすくなってしまう傾向がありますよね。
こうした理由から『閉鎖的な空間』は、保育士の人間関係が最悪になりやすい原因の1つといえます。
2.業務の負担に偏りがある
保育士の人間関係が最悪になりやすい2つ目の理由は、『業務の負担に偏りがあること』です。
保育士の仕事は、子どもを保育することだけではありません。




































































































































































































書類の作成や行事・制作物の準備など、多くの仕事をしています。
これらの業務は、同じクラスの保育士同士が協力して行うべきものです。
しかし、担当するクラスに新人保育士がいるため、
- 先輩保育士が多く負担しなければいけない
- 先輩保育士が「勉強だから」と言って、後輩(新人)保育士に多く振り分ける
などして、業務の負担が偏るケースもあります。
このような業務の偏りは、不満や不満感を生み出し、人間関係を悪化させる原因です。




































































































































































































私も行事の準備を先輩保育士(正規職員)とやっていましたが、「子どもがいるから」という理由で、ほとんど私が負担していました。
もちろん仕方ないことではありますが、やはり不満に感じたことがありましたね。
こうした理由から『業務の負担に偏りがあること』は、保育士の人間関係が最悪になりやすい原因の1つといえます。
3.保育士同士を比較する
保育士の人間関係が最悪になりやすい3つ目の理由は、『保育士同士を比較すること』です。
当然、保育士といっても、1人ひとりの経験やスキルは異なります。




































































































































































































1人ひとりの経験やスキルを把握し、協力しながら保育できることが理想ですよね。
しかし、中には、残念なことに他の保育士と比較して、優劣を付けてしまう人がいます。
- 「〇〇さんはこんなに仕事できるのに、なんであなたはできないの?」
- 「もっと〇〇さんを見習いなさい。」




































































































































































































このような言葉は、比較された相手を傷つけ、やる気やモチベーションを低下させてしまう原因ですよね。
先輩保育士から同じ時期に入職した保育士あるいは、後輩保育士と比較されることは仕方ないかもしれません。
しかし、職員同士を比較したり、叱責された側は、萎縮してしまい、本来の力を出すことができなくなってしまいます。




































































































































































































私も主任保育士から比較・叱責されたことで萎縮し、人間関係がうまくいかず「最悪…。」と思っていました。
こうした理由から『職員同士を比較すること』は、保育士の人間関係が最悪になりやすい原因の1つといえます。
4.職員を差別する
保育士の人間関係が最悪になりやすい4つ目の理由は、『職員を差別すること』です。
残念なことに、先輩保育士や主任保育士・園長が、特定の保育士をひいきし、他の保育士を差別しているケースがあります。




































































































































































































実際に、私もありました。
私が実際に経験した差別は、下記の通りです。
- ひいきしている保育士
-
- 仕事でミスしても、全力でカバー・フォローする
- 仕事の負担を減らす
- 優しく接する
- 差別している保育士
-
- ミスをしたら、必要以上に叱責する
(精神的に追い詰め、退職させる=パワハラ) - 1人でやりきれないほどの量の仕事を振り分ける
- 接し方が厳しい
- ミスをしたら、必要以上に叱責する




































































































































































































このような職場だったので、『本当に嫌われたら終わり』の状態で、怖かったですね…。
なぜ、『ひいきする保育士』・『差別している保育士』を作っているのか理由はわかりません。
差別している保育士には、さまざまな理由があるのでしょう。
しかし、理由はどうあれ、職員を差別することは許されることではありません。




































































































































































































保育士の前に、「人としてどうなんだ?」というレベルです。
こうした理由から『職員を差別すること』は、保育士の人間関係が最悪になりやすい原因の1つといえます。
5.先輩保育士の言い方がきつい
保育士の人間関係が最悪になりやすい5つ目の理由は、『先輩保育士の言い方がきついこと』です。
保育士は、子どもの命を預かっているので、場合によっては、きつく指導されることもあります。




































































































































































































それは子どもの命を預かっている仕事である以上、仕方ないことです。
しかし、常に言い方が厳しい先輩保育士もいるため、後輩保育士が萎縮してしまったり、悩んでしまったりするケースがよくあります。




































































































































































































Yahoo知恵袋にも、このようなお悩みが投稿されていました。
保育士1年目の女です。
(中略)
2年目の先輩保育士は同じクラスの担任なのですが、言い方がきつく「ちゃんとやってる?」「大丈夫?やっていける?」「自分で動いて」などと何度も言われていまいます。
保育士続けられる自信が無いです。
(後略)
引用:Yahoo知恵袋
保育をしている中で、子どもの身に危険が及ぶ場合は、厳しい言葉をかけられてしまうことは仕方ありません。
ですが、先輩保育士の言い方がきついと、後輩保育士のモチベーションを下げ、自信をなくしてしまうことが多いです。




































































































































































































私も言い方がきつい先輩保育士が多かったので、「もうちょっと言い方考えてよ…。」と思うことが多かったですね…。
こうした理由から『先輩保育士の言い方がきついこと』は、保育士の人間関係が最悪になりやすい原因の1つといえます。
6.先輩保育士のあたりが強い
保育士の人間関係が最悪になりやすい6つ目の理由は、『先輩保育士のあたりが強いこと』です。
子どもの保育はもちろん、業務をしていく中で、
「こういうときはどうしたら良いのだろう?」
「先輩からアドバイスをもらいたいな。」
と思う場面は多くあります。
しかし、なぜか他の保育士には優しいのに、自分だけにだけ厳しく接する(あたりが強い)先輩保育士もいます。




































































































































































































Yahoo知恵袋でも、このようなお悩みを抱えた保育士さんがいました。
新卒保育士です。
私に当たりの強い先輩のことについて悩んでいます。
わからないことを質問をしても「自分で考えて」と言われ、質問をせずに自分で考えて行動するとあーだこーだと言われます。
他にも「もう半年でしょ?ほんとに大丈夫?」とか言われたり何か仕事の内容で話しかけると目も合わせずに「あーうん、おけ」みたいな反応をされてしまいます。
忙しい時に質問せずに午睡中や人手がたくさんいる時に質問をしているのに、です。
(中略)
もう話しかけるのも、その場にその先輩がいるのも怖くなってしまいます。
毎日毎日チクチクする言葉を言われ、家に帰って泣いてばかりです。
(中略)
年度終わりまでやっていけるのか不安です。
最近、メンタルが壊れてきていて泣いてばかりだし不眠気味です。
(後略)
引用:Yahoo知恵袋




































































































































































































私も全く同じ経験をしたことがあり、とても辛かったですね…。
やはり、こうした状況だと後輩保育士にとっては、先輩保育士に声をかけることが怖くなってしまうため、悩みの種になりやすいです。
年度途中に担当クラスが変更になることはないため、1年間耐えるしかなくなってしまいます。




































































































































































































なかなか精神的にも辛いものです…。
こうした理由から『先輩保育士のあたりが強いこと』は、保育士の人間関係が最悪になりやすい原因の1つといえます。
7.相手の気持ちを考えられない
保育士の人間関係が最悪になりやすい7つ目の理由は、『相手の気持ちを考えられないこと』です。
保育士の仕事は、クラスの保育士が声を掛け合い、協力しながら行うものです。




































































































































































































そのため、保育士の連携・チームワークがとても重要になります。
ですが、相手の気持ちを考えず、
- 人には指示するのに、自分は何もしない保育士
- 自分の言いたいことだけをいう保育士
言い方がきつい or 相手の話を聞かない など - 自分の感情のまま接する保育士
自分の機嫌が悪いと周囲に対してあたりが強くなる など
残念なことに、こうした保育士も一定数います。




































































































































































































実際に私が勤めた職場にも上記のような保育士がいたので、非常に困りました…。
当然、保育士同士の人間関係も悪かったですね…。
こうした保育士は、自分の言動や行動によって、相手がどんな気持ちになるのかを考えられていない証拠です。




































































































































































































当然相手のことを考えられる保育士であれば、上記のようなことは起こらないはずですよね。
こうした理由から『相手の気持ちを考えられないこと』は、保育士の人間関係が最悪になりやすい原因の1つといえます。
8.先輩保育士の指導方法が自分に合っていない
保育士の人間関係が最悪になりやすい8つ目の理由は、『先輩保育士の指導方法が自分に合っていないこと』です。
新卒保育士の場合、保育経験がないので、右も左もわからない状態からスタートします。
いくら保育実習を経験したとしても、実際に保育士として勤務すると、やることはもちろん、責任も違います。
だからこそ、先輩保育士から
- 子どもや保護者のこと
- トラブル発生時の対応
- 書類作成や行事の準備のやり方 など




































































































































































































こうした指導を受ける必要があります。
しかし、先輩保育士によっては、全く指導をしない・指摘しかしない保育士もいます。
そうすると、後輩保育士は、先輩保育士に
- 相談しづらい
声をかけるのも怖い - 萎縮する
こうした状況になり、人間関係で悩んでしまう原因になります。




































































































































































































誰でも、仕事を教えてもらえず、指摘ばかりされていると、嫌ですよね…。
こうした理由から『先輩保育士の指導方法が自分に合っていないこと』は、保育士の人間関係が最悪になりやすい原因の1つといえます。
9.保育観が合わない
保育士の人間関係が最悪になりやすい9つ目の理由は、『保育観が合わないこと』です。
保育士は1人ひとり考え方や価値観は異なるため、子どもに対する考え方や保育の理想像を持っています。
そのため、同じクラスを担当していても、保育観が合わないということはよくあります。




































































































































































































私も同じクラスを担当した先生と、「保育観が合わない」と感じたこともあります。
HoiClueは、保育士を対象に『保育観の違い』についてアンケート調査を実施、結果を公表しています。


回答した約7割の保育士が、『保育観の違い』を感じている結果となりました。




































































































































































































結構多いですよね。
同じ保育士といえども、考え方や価値観はもちろん、経験も違うので、保育観が合わないことは致し方ないことです。
ですが、せめて子どもにとってプラスになることであれば良いですが、マイナスになる場合、
- 「〇〇先生の対応、どうなの?」
- 「子どものことより自分中心だよね。」
など、悪い印象を持ってしまう or 持たれてしまうケースがあります。




































































































































































































やはり、こうした状況では、良い保育をすることもできませんし、保育士同士の人間関係にも影響を及ぼす可能性が高いことがわかりますよね。
こうした理由から『保育観が合わないこと』は、保育士の人間関係が最悪になりやすい原因の1つといえます。
10.悪口をいう
保育士の人間関係が最悪になりやすい10こ目の理由は、『悪口をいうこと』です。
『閉鎖的な空間』でもお話したように、閉鎖的な空間で長時間一緒に過ごす中で、人間関係は複雑になりがちです。
そのため、一緒に仕事をしている人の悪い面(短所)にばかり注目し、周囲の人と悪口をいう保育士も残念ながら多いです。




































































































































































































私が勤務した職場でもこうしたことがあり、「保育士同士の人間関係が最悪だな…。」と感じることが多かったです。
悪口を聞いている側・言われた側にとって、やはり気持ちの良いものではありませんよね。
また、悪口を聞いて嫌な気持ちになるだけでなく、
「自分も言われているのではないか?」
など、悩みの種になってしまう可能性が高いです。
こうした理由から『悪口をいうこと』は、保育士の人間関係が最悪になりやすい原因の1つといえます。




































































































































































































悪口をいう人の心理や特徴について知りたい方は、こちらの記事でも詳しく解説しています。
11.大変な仕事を押し付ける
保育士の人間関係が最悪になりやすい11こ目の理由は、『大変な仕事を押し付けること』です。
保育士の仕事は、子どもを保育することだけでなく、さまざまな仕事を行っています。
- 書類の作成
- 行事の準備
- 制作物の準備 など
これらの仕事は、皆で平等に負担するのが基本です。
しかし、
「新人だから or 若いから…。」
「勉強のために…。」
などと言って、大変な仕事を押し付けられるケースも多いです。
先輩保育士と新人(若い)保育士と比べると、
- 担当クラスを引っ張る立場(クラスの責任者)
- 後輩の指導 など
どうしても責任が重い立場になります。
ですが、だからといって、後輩保育士に仕事を押し付けて良い理由にはなりません。
大変な仕事を押し付けられた後輩保育士は、先輩保育士に対して、
- 悪いところしか目がいかなくなる
- 不信感を募らせてしまう
このような状態になりかねません。




































































































































































































人間関係にも悪影響ですよね。
こうした理由から『大変な仕事を押し付けること』は、保育士の人間関係が最悪になりやすい原因の1つといえます。
12.自分のミスを認めたくない
保育士の人間関係が最悪になりやすい12こ目の理由は、『自分のミスを認めたくないこと』です。
子どもの保育をしている中で、
- 保護者から言われたこと(連絡事項)を忘れてしまった
- 保護者に伝えなければいけない連絡を忘れてしまった
- 子どもにケガをさせてしまった
など、保育士の不注意によってミスしてしまうこともあります。




































































































































































































特に子ども同士のトラブルで、咄嗟に対応しても間に合わず、ケガをさせてしまうことも多かったですね…。
子どもはもちろん、保護者にも申し訳なかったと反省するばかりでしたね…。
こうしたミスやトラブルが発生したときに、
- 「私は悪くない。」
- 「トラブル回避できなかったのは、あなたのせい。」
など、自分のミスを認めなかったり、人のせいにしたりする保育士も残念ながら多いです。




































































































































































































私もこうした経験をしたことがありますが、X(旧Twitter)をみてみると、似たような経験をしている方がいました。




































































































































































































やはりこうした状況では、保育士同士の人間関係はもちろん、子どもを保育する上でも悪影響しかありません。
こうした理由から『自分のミスを認めたくないこと』は、保育士の人間関係が最悪になりやすい原因の1つといえます。
13.自分の価値観を押し付ける
保育士の人間関係が最悪になりやすい13こ目の理由は、『自分の価値観を押し付けること』です。
保育経験が浅いうちは、先輩保育士の姿をみるだけでなく、自分でも考えながら保育をしている人がほとんどです。
先輩の姿を参考にしたり、アドバイスをもらいながら、
- 自分らしい保育スタイルを見つけていく
- 保育士としてだけでなく、1人の社会人として成長する




































































































































































































あくまで個人的な考えですが、私はこうしたことが大切だと思っています。
しかし、自分で考えてやろうとしている後輩保育士に対して、
- 「なんのためにやるの?」
- 「そんなの、意味がない。」
- 「自分が新人のときは、こうだった!」
など、否定したり、誰かと比較するような発言をしたりするほか、自分の価値観を押し付ける(押し通す)先輩保育士もいます。
このような先輩保育士がいると、後輩保育士は
「何をやっても否定されたり、比べられたりするのではないか…?」
と思い、人間関係に悩んでしまうケースも少なくありません。




































































































































































































私が勤めていた保育園でも、こうした先輩保育士もいて、本当に怖かったですね…。
こうした理由から『自分の価値観を押し付けること』は、保育士の人間関係が最悪になりやすい原因の1つといえます。
14.連絡事項を伝えない
保育士の人間関係が最悪になりやすい14こ目の理由は、『連絡事項を伝えないこと』です。
保育士は、保護者から連絡事項を聞き、クラスの保育士全員が把握した上で保育を行う必要があります。




































































































































































































子どもが安全に、健康に1日過ごすためにも、欠かすことができない業務の1つです。
しかし、連絡事項をしっかり把握した上で、保育を行う必要があるのにもかかわらず、連絡事項を伝えない園長や保育士もいます。




































































































































































































「本当にこんなことがあるの?」という状態ですが、実際に私もこうした経験があります。
経験豊富な保育士からみると、私にも至らない点も多かったと思いますが、だからといって連絡事項を伝えなくて良い理由になりません。
このような状況だったので、「人間関係が最悪すぎる…。」と感じながら仕事をしていました。




































































































































































































とにかく毎日、仕事に行くのが苦痛でしたね…。
こうした理由から『連絡事項を伝えないこと』は、保育士の人間関係が最悪になりやすい原因の1つといえます。
ここまでは、保育士として勤務した私の実体験から、保育士の人間関係が最悪になりやすい理由について紹介しました。
- 閉鎖的な空間
- 業務の負担に偏りがある
- 職員同士を比較する
- 職員を差別する
- 先輩保育士の言い方がきつい
- 先輩保育士のあたりが強い
- 相手の気持ちを考えられない
- 先輩保育士の指導方法が自分に合っていない
- 保育観が合わない
- 悪口をいう
- 大変な仕事を押し付ける
- 自分のミスを認めたくない
- 自分の価値観を押し付ける
- 連絡事項を伝えない
ここまで読んでみて、
「本当に保育士の人間関係って最悪なんだ…。」
このように感じた方も多いかもしれませんね。




































































































































































































私もきっと学生の立場だったら、このように感じていたことでしょう…。
保育士の人間関係が最悪と言われているのは、昔からずっとで今も変わっていません。
実際に保育士として勤務した私は、
- 保育士はこうした環境が当たり前と思っている経験豊富なベテラン保育士が多い
- 女性特有の人間関係の難しさ
この2つの理由が人間関係が最悪と言われ続けている原因ではないかと思っています。
保育士は、人間関係が最悪と言われていますが、それと同時に、『保育士は闇が深い』とも言われています。




































































































































































































保育士の闇が深いと言われている理由については、こちらの記事で詳しく解説しています。
保育士が抱えている問題を1つひとつ解決し、1人でも多くの保育士が働きやすい環境で活躍できる職業になるのを願うばかりです。
まとめ
この記事では、保育士の人間関係が最悪でリスクが高い理由と、人間関係の悩みにどう対処していくべきかについて、お話をしてきました。
保育士の人間関係が最悪になりやすい理由は、下記の通りです。
- 閉鎖的な空間で仕事をしているから
- 職員同士を比較したり、差別したりする人がいるから
- 先輩保育士の言い方やあたりがきついから
- 大変な仕事を押し付けたり、自分の価値を押し付けたりするなど、相手の気持ちを考えないから
いかがでしたか?
残念ながら、保育士の人間関係の難しさは、昔も今も変わっていません。
そのため、
「本当に保育士になって大丈夫なのか?」
「保育士を続けていけるのかが心配…。」




































































































































































































と、悩む人は多いですよね。
しかし、なかには人間関係が良好で、働きやすい保育園もあります。
保育士の人間関係が良好で働きやすい保育園を見つけるためには、




































































































































































































この4つが大切です。
保育士の人間関係について、不安なことがたくさんあることでしょう…。
しかし、保育士を目指している皆さんには、
「人間関係が良くて、この保育園に勤務してよかった!」
「保育士になってよかった!」
と思える職場を見つけてもらい、楽しく働くことができるのを願っています。